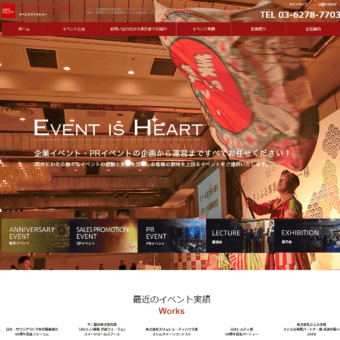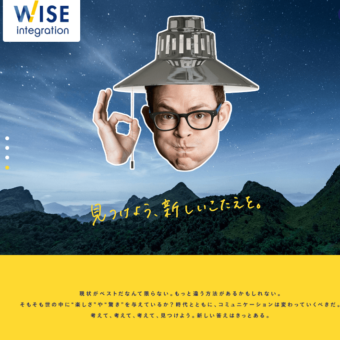イベント企画において重要なことは?業者に依頼する場合の注意点も紹介

もくじ
イベント企画を成功させる上での重要な考え方とは?
会社や個人の活動を宣伝する方法としてイベントはかなり有効的です。たくさんの人に集まって楽しんでもらうという「体験」を通して認知されれば、ポジティブなイメージを広い範囲に浸透させることができ、その後の活動に大きな良い影響が生まれます。
しかしそれにはイベントをただ開催するのではなく成功させることが必要です。せっかく企画したイベントも、失敗してしまっては費用や時間の無駄になってしまいます。では一体どんな考え方で進めればイベントは成功するのでしょうか。
イベントには必ず目的がある
イベントというのは、ただ人がたくさん集まればそれで成功という単純なものではありません。どれだけ人が集まったとしても、開催した目的が達成されていなければそれは失敗です。たとえば、商品の宣伝のために催されたイベントが、出演した有名人の印象ばかりが残ってしまう結果に終わったとしたらどうでしょうか。
人気のある芸能人などに出演してもらうのは確かに集客には効果的ですが、ファンイベントのようになってしまったのなら失敗だといえます。外部のお客さんを呼ぶイベントではなく社内イベントなどの場合も同様です。
イベントを行うからには、何か具体的な目的がなければいけません。業績の良い社員の表彰式や、新入社員の入社式、社員全員参加の親睦会などは、会社全体の士気が高まったり、社員同士の交流が深まったりするものであれば意味のあるイベントになります。
内容の充実度も大事
目的を明確に持ち、その達成のために最適と思える内容にする、これはイベントを開催する上での基本的な考え方ですが、このとき気を付けなければいけないことがあります。間違いなく目的が達成できるような道筋というのは、簡単に言ってしまうと、面白味に欠けてしまっていることがあるものです。
例えば、説明会を想像してみると分かりやすいかもしれません。ひたすら淡々と会社や商品の説明を話されるだけでは来場者の興味を持続させるのは難しいですが、参加型のゲームのような要素を追加することで満足度を高められる可能性はあります。
イベントといってもエンターテイメント性の高いものばかりとは限らず、学術大会などの真面目なものもイベントと呼ばれますが、どんなジャンルでも共通して「内容が充実していること」は良いイベントの必須条件です。目的やターゲット、開催場所といった部分だけではなくイベント自体の中身についても忘れず意識しておく必要があります。
楽観視しすぎない
「これだけの準備をしたからには当日何か問題が起こったりしても何とかなるはず」や「現在人気のアイテムに関するイベントだからいくらでも人は集まるだろう」といった楽観的過ぎる考え方は間違いです。かといってネガティブになり過ぎるのもよくありませんが、イベントという多くの人や費用が動くものを開催するに当たっては、少し考え過ぎというくらいさまざまなことについて考えを巡らせる必要があります。
事前にきちんと準備をしていても、実際その日になってみるまで何が起こるかは誰にも分からないものです。決定的にカバーしようのない問題が発生してしまった場合は仕方ありませんが、多少のトラブルであれば容易にフォローできるような態勢を整えておくことは必須だといえます。
そしてイベント内容についても、ターゲットにするのは確実に結果が分かるコンピュータなどではなく「人」なので、どんなに自信のある内容だとしてもできる限り検討を重ねるのがおすすめです。
成功するイベント企画の特徴とは?
 東京の中でも、イベント企画は様々なところで行われています。
東京の中でも、イベント企画は様々なところで行われています。
学生だけでなく社会人のイベントも非常に多く大成功を収めているところも珍しくありません。
では、どのようにしたら大成功するでしょうか。
その特徴をいくつか見ていきましょう。
企画の段階で考えておきたいこと
イベント企画を成功させるためには、企画の段階でしっかりとした内容にしておかなければなりません。
そのための特徴は、まず目的が明確になっていることが重要です。
目的は、そのイベントの方向性を示すことを意味していますので、方向性が明確ならば力を注入する部分も明確になります。
ですが目的がブレていると、一点に力を集中させることができず何ら魅力のない結果となってしまいます。
次に、そこに参加するメンバーを決めなければなりません。
メンバーを決める場合のポイントは、適材適所です。
とにかく人数だけ集めれば何とかなるわけでもなく、より良い結果を出す為には誰をどこに配属させるかをその人の能力を考えながら決めていくことが重要になるでしょう。
後は、日付や場所を明確にしなければなりません。
基本的に開催する日付がゴールになりますが、ゴールが明確でないといつの段階で何を準備したらよいのかがわからなくなり、予定していた内容が完成しない可能性が高くなります。
このとき、ゴールに到達するためのスケジュールを組むことが可能なのかを明確にし、可能でなければゴールを先延ばしするか、ゴールの位置を動かさずにスケジュールの内容を減らして対応するしかありません。
もし、今の状態で可能でも少し予備日などを設けて余裕を持たせておくことも大事になります。
進ちょく状況を把握することも大事になる
東京でイベント企画を大成功させるためには、進ちょく状況が明確になっていることが大事になります。
これは、うまくいっているイベントの特徴といっても過言ではありません。
進ちょく状況を調べるためには、誰が・いつ・何を・どれだけ実行しているかを明確にし、現在の状況を明らかにしていきます。
その中で必ず無駄な動きが出てきますので可能なかぎり省く必要があります。
次に、イベントの準備に参加している人たちが全員で情報を共有できる仕組みを作っておくことも大事といえます。
例えば、1か所に全員がいる場合には一冊のノートを作り必ずイベントの企画に参加する人が仕事を開始する前にそのノートを一読しておく仕組みを作るだけで、全体がスムーズに流れていくでしょう。
もし、それぞれが離れている場所にいる場合に関しては、インターネット上のツールを使ってタスク内容を管理する方法もあります。
イベントにおける集客を行うときの特徴とは
イベント企画をする場合、最終的に集客を目的としますが、この時どのように集客をしていくかが問題になります。
一つは、インターネットのコンテンツを通じて行う方法です。
この場合、コンテンツ自体が果たして上位表示されるかあるいは特定の会社とうまくリンクしているかなどを考えなければいけません。
上位表示させるためには、ある程度早い段階でコンテンツを作っておく必要があります。
最低でも、イベントが行われる6カ月より前の段階で作っておいた方がよいです。
告知に必要な期間は、3か月以上前から告知をした方が多くの参加者を募ることができるでしょう。
逆に半年より前の段階で告知をしたとしても、予定が後になり過ぎてしまうため告知をする意味が薄れてしまいます。
チラシを配る場合には、場所を限定して配る必要があるでしょう。
イベントに参加する人の属性などを考えると、配る場所と時間帯なども少しずつ明確になってきます。
イベント企画で成功させるための特徴としては、まず計画の段階でゴールを明確にすることです。
ゴールが明確になれば逆算しながらいつまでに何をしなければならないかがわかります。
次に、進ちょく状況を明確にしておくことが必要です。
現在誰がいつどこで仕事をしているのか、全体の進み具合は問題ないのかを全員で共有できるとよいでしょう。
最後に、集客するための仕組みをあらかじめ作っておくとよいです。
集客をする場合にはイベントの3カ月前ぐらいから行えば十分です。
このように、準備を明確にして全体を把握することでより成功しやすいイベント企画が完成します。
イベント企画のスケジュールはどうなっている?
 大規模なイベントを行う予定ならば、できる限りたくさんのお客を集めたいと考えるでしょう。
大規模なイベントを行う予定ならば、できる限りたくさんのお客を集めたいと考えるでしょう。
そのためには、きちんとしたイベント企画が必要となるため、自分たちで行うのではなくプロに任せたほうがよいです。
現在ではイベントの企画や制作を専門とする会社があります。
ここでは、イベント会社に頼んだとき、どのようなスケジュールで進行していくのか説明したいと思います。
スタッフによるヒアリングから始まる
イベント会社に仕事を頼みたいと連絡を取ると、スタッフと話し合いをすることになります。
そのヒアリングの場では、イベントで行いたいことや開催予定日を話す必要があるので、大まかな構想を決めておきましょう。
もしも、イベントを開催するのが初めてで、どのようなことを考えておけばよいのか分からないのなら、連絡を取った時点でスタッフに相談してみましょう。
相手もプロなので、何も分からない状態でヒアリングに臨んでも、しっかりとした対応してくれるでしょう。
しかし、その場合は持ち帰って検討しなければいけないので、ヒアリングの回数が増えてしまいます。
そうならない為には、決めておくべき必要事項を事前に聞いて、1回目のヒアリングで話せるようにしておきましょう。
なお、イベント会社はプロなので、要望通りのイベントを開催してくれるだけではありません。
これまで蓄積してきたノウハウをしっかりと使って、要望以上のイベントを行ってくれます。
いろいろな提案をされるので、しっかりとスタッフと話し合い、完璧なイベントを開催できるようになりましょう。
イベント企画書と見積もりをもらう
ヒアリングが終わったのなら、どのようなイベントになるのか、企画書を作成してもらうことになります。
企画書を読んで仕事を依頼してもよいと決心したのなら、イベントの開催予定日に向けて行動を始めましょう。
もしも、内容が気に入らなかった場合は、再度ヒアリングを行って、企画書を作り直してもらうことになります。
ここで妥協してしまうと、すべてにおいて満足できない可能性があるため、納得できるまで何度でも作り直してもらったほうがよいです。
また、見積もりを作ってもらえるため、イベントを開催するための費用も事前に確認できます。
予算を伝えておけば、それに収まるようにイベントを企画してくれるので、決まっているのなら最初に伝えておきましょう。
もちろん、見積もりが納得できない場合も、再度ヒアリングを行って、やり直してもらうことが可能です。
イベントの開催に向けて動きだす
企画書と見積もりに納得ができて、仕事を依頼したのなら、あとはイベント会社が開催に向けてさまざまなことを頑張ってくれます。
会場の手配やお客様を呼び込むためのPRなど、イベント開催に必要なことはすべて行ってくれるので、心配せずに任せて大丈夫です。
もちろん、開催するにあたって、主催者側が注意すべきポイントも教えてくれるため、何ごとも問題なく終了させられます。
もちろん、後片付けも、サービスに含まれているので、開催後も苦労することはないでしょう。
これまで多くのイベントを成功させてきた実績を持つイベント会社ならば、企画も制作も完璧に行ってくれます。
これまでどのようなイベントを手がけたか、ホームページ上で公開するところもあるので、選ぶときに参考にするとよいでしょう。
もしも、イベント会社を決めかねているのなら、いろいろなところにコンタクトを取って、ヒアリングを行ってもらうとよいです。
あとは、それぞれの企画書と見積もりを見比べて、より希望に近いイベント会社を選定しましょう。
イベント企画会社に依頼する際の注意点って?
 さまざまな企業によって、イベントは開催されます。その種類や業種もさまざまです。顧客は、イベントが面白そうだと思えば参加し、その企業の存在を知ることになります。イベント企画会社は、イベントを開催するために企業に依頼されてイベントを企画・運営する会社です。イベントプランナーが、企画から開催まで成功させるためにいろいろと考えてくれます。
さまざまな企業によって、イベントは開催されます。その種類や業種もさまざまです。顧客は、イベントが面白そうだと思えば参加し、その企業の存在を知ることになります。イベント企画会社は、イベントを開催するために企業に依頼されてイベントを企画・運営する会社です。イベントプランナーが、企画から開催まで成功させるためにいろいろと考えてくれます。
費用はかかるが依頼するほうが成功する
会社や団体などがイベントを開催したいと考えたときに、自社の人間だけで企画から運営まで行なうとなると、時間も労力もかかります。もし、普段からイベントに関する仕事をしていれば簡単に動くことができますが、そうでなければなかなか難しいでしょう。
無理に自分たちだけで企画しようとすると、本業にも負担がかかってしまいます。そこで活躍するのがイベントプランナーの存在です。イベントプランナーは豊富な経験や実績があります。イベントの企画・運営を本業とするイベントプランナーに依頼をすることによって、行いたいイベントを成功に導いてくれます。もちろん、外注することによって費用はかかってしまいますが、イベントを成功させることが出来れば企業の宣伝にもなりますし、集客数も見込めるため、それ以上の利益を得ることができるでしょう。
意向にあったイベントを開催してくれる
イベント企画会社に依頼する場合の注意点は、きちんと自分達の意向にあったイベントを開催してくれるかどうかということが第一です。どのようなイベントになるかは完成してみないとわからないものなので、はじめに見極めるのは難しいかもしれません。
いいイベントプランナーを探すことができれば、イベントの成功にもつながるので、まずは依頼する前に、口コミや評判などを見てみることをおすすめします。そして候補を見つけることができたら、そのイベントプランナーが手がけたイベントの実績なども参考にしましょう。その中から自分達の会社にあったイベントプランナーを見つけることが重要になってきます。
完成させるための会社選びが大事
イベント企画会社に依頼するとなると、当然費用がかかります。コストパフォーマンスも大切ですが、あまり安いからという理由で決めないほうがいいでしょう。安くてもあまりいいイベントではなかったら、宣伝にもなりませんし、集客にもつながりません。
また、イベント企画会社の規模も重要です。大きなイベントを開催する場合には、さまざまな人が関わることになります。いろいろな情報を収集してもらう必要があるので、企画会社の規模は重要です。小規模な会社にお願いすると、費用も安く済むかもしれませんが、その分人数が足らないといったことになってしまいます。どのくらいの人員が必要になるのかは、あらかじめ考えておくとよいでしょう。
イベントの開催を考えるときに、自分達で企画から開催までを担おうとすると、かなりの時間や労力が必要になります。さらに、本業の時間を割いて準備をしなければなりません。ですから、イベントの企画は専門の業者にお願いすることがおすすめです。そのイベントを企画してくれる業者選びも重要で、費用の面だけではなく、イベントの規模からどれぐらいの人数が必要なのかなども考えておきましょう。
イベントは開催してみるまで成功するかどうかはわからないものです。そこで、イベントプランナーの経験と実力が命運を左右します。経験豊富なイベントプランナーが居る会社に依頼をすることで、失敗のないイベント作りをしましょう。
まとめ
イベントというのは友人同士の集まりのように「なんとなく」で開催できるものではありません。具体的な目的を定め、それに向けてあらゆることを進めていく必要があります。参加者に有意義だと思ってもらえるイベントを作り、ひいては新たなビジネスチャンスを生み出すためには、徹底した事前準備が肝心です。
種類ごとのイベント企画情報
セミナーイベント企画の流れと注意点
展示会イベント企画の流れと注意点
演奏会などの文化系イベント企画の流れと注意点
販促イベント企画の流れと注意点
ワークショップイベント企画の流れと注意点
コンベンションイベント企画の流れと注意点
スポーツイベント企画の流れと注意点