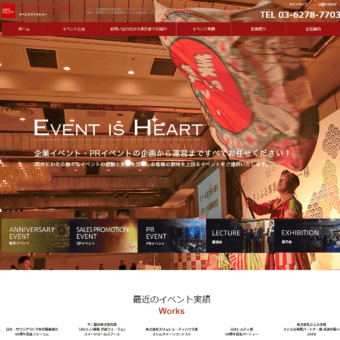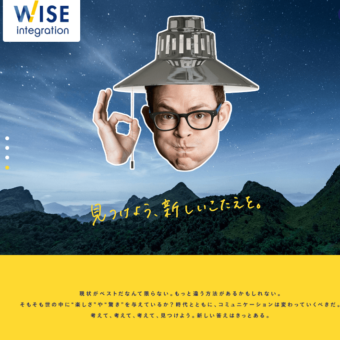イベントのキャンセルポリシーとは?ポイントや例文まで紹介!

返金をめぐってお客様とトラブルになったなど顧客とのトラブルを恐れていませんか?解決策のひとつが「キャンセルポリシーの明確化」です。キャンセルポリシーを設けることでトラブルを防ぎ、安心してイベント運営を続けられるようになります。この記事では、キャンセルポリシーの目的、例文をまとめました。小規模イベントやセミナーを運営している方は、イベントに合ったキャンセルポリシーを作りましょう。
キャンセルポリシーとは?目的と役割をわかりやすく解説
キャンセルポリシーとは、予約や申込をキャンセルした場合のルールを定めた取り決めです。明確に示すことで顧客とのトラブルを未然に防ぎ、信頼性を高める効果があります。
「申込後の返金不可」「開催3日前まではキャンセル可能」など必要な情報を入れてください。まずは自分のサービスに「なぜキャンセルポリシーが必要なのか」という目的を整理しましょう。
キャンセルポリシーを設けるメリット
ルールがあいまいだったことにより、キャンセル対応に追われたり、返金トラブルが発生したり運営の負担が大きくなることが想定されます。キャンセルポリシーを設けるメリットを3つ紹介します。
無断キャンセルや直前キャンセルによる損失を防ぐ
直前キャンセルは売上損失に直結します。1席でも埋まらなければ赤字になる小規模イベントでは、とくにキャンセルされないことが重要です。
もしも飲食イベントで当日キャンセルが出ると、食材や人件費が無駄になってしまうことが懸念されます。イベントの参加キャンセルには期限を設け、損失を最小化しましょう。
顧客とのトラブルを未然に防げる
キャンセルポリシーのルールがないと「なぜ返金できないのか」と揉めます。キャンセルポリシーはイベント運営側と顧客の約束事です。たとえば、キャンセル連絡のタイミングが記載がない場合は、連絡期限が曖昧なことで顧客が混乱することも想定できます。
また、一部の人だけ返金されたりキャンセルが認められたり、対応に差があると主催者への不信感が広がって今後の参加意欲が下がります。事前にルールを提示することで、顧客は納得しやすくなります。
たとえば「キャンセルは7日前まで、それ以降は全額負担」と記載することで説明がしやすくなります。トラブル回避のため、明記しておくことが必須です。
運営者・顧客双方の安心感を高められる
ルールがあることで、双方が納得した上で安心して契約できます。透明性があることで「信頼できるイベント」と評価されやすくなるでしょう。信頼性の高い運営者が開催するイベントでは、チケット購入に関して必ずキャンセルポリシーを公開しています。
イベントを成功させるだけでなく顧客からの信頼を得たいなら、必ずキャンセルポリシーを整備しましょう。
キャンセルポリシーを作るときのポイント
顧客とのトラブルを回避するために具体的に設定すべき4つの要素を解説します。これから紹介するポイントを踏まえて作成すると、スムーズに作れるでしょう。
いつまでキャンセルできるのか期限を明確にする
「いつまでならキャンセル可能か」を決めましょう。日数が曖昧だと顧客が混乱します。たとえば「キャンセルにつきましては、開催日の7日前までにご連絡いただければキャンセル料は発生いたしません。」という文言があれば明確です。
それ以降のキャンセルについても全額負担なのか、返金の有無などを記載すると親切です。イベントの業種や、他の参加希望者がキャンセル枠を埋められる期間に合わせて設定してください。
期限を過ぎた場合の返金・対応ルールを定める
期限後の対応も明記が必要です。「返金不可」か「一部返金」かを事前に決めることで、トラブルを避けられます。「3日前まで50%返金、それ以降は不可」など曖昧な表現は避けて明記しましょう。
ルールが定まっておらず参加者が返金対応に不満があった場合、SNSに拡散されネガティブな口コミが広がる可能性があります。イベントの評判にも関わるため、明確な数字で伝えるのがポイントです。
体調不良や災害など例外条件を追記する
体調不良など不可抗力に配慮する文を入れると親切です。全額負担だと、顧客が納得せずに不満を抱きやすくなります。万が一、新型コロナウイルスのような感染力の強い感染症罹患者が参加してしまうと、イベント会場全体に感染リスクが広がってしまうかもしれません。
例外として感染症罹患者に対しては「医師の診断書がある場合は返金可」など記載し、対応の柔軟性を残すことで信頼が高まります。体調不良以外にも、行きたい気持ちが合っても参加できない災害の被災者に対しても同様の対応をすることをおすすめします。
契約書・予約サイト・店頭など明記する場所を決める
キャンセルポリシーは、顧客が見える場所に明記することが大切です。「知らなかった」と言われるのを防ぐためです。予約ページ、契約書、店舗掲示などに掲載してください。事前決済の場合は、入金時に必ず目を通してから申し込むように場所を設けてください。
顧客が目にする場所へ必ず明示しましょう。
キャンセルポリシーの例文集
キャンセルポリシーをこれから考える方でも、作りやすくなる例文を作成しました。ポイントは、具体的な数値を明記し、誰が読んでも同じ解釈ができるような分かりやすい表現にすることが大切です。
例文1:医療・サロンなど顧客に配慮したケース
日付変更を可能にする柔軟な対応は医療サービスやサロン、プライベートレッスンなど、個人の都合に寄り添うことが重要なサービスに有効です。
例文としては「お客さまのご体調不良や急なご用事によるキャンセルは、前日までにご連絡いただいた場合、1回のみ日程変更が可能です。」が挙げられます。
このように、サービスの特性に合わせた柔軟なルールを設けることで、お客さまとの信頼関係を築きやすくなります。
例文2:申込後すぐに返金不可とするケース
材料費や人件費が即時発生する業種に有効です。原価率が高く、損失が大きいからです。
「お申し込み完了後のキャンセルにつきましては、いかなる理由においても返金はいたしかねます。ご参加が難しくなった場合でも、参加費の返金はできませんので、あらかじめご了承のうえお申し込みください。」
ただし代理参加は可能です。ご希望の方は事前にご連絡ください。など付け加えるとキャンセル率は減らせるでしょう。「申込時点で契約が成立する」旨を明記すると、法的にも安心です。
「返金不可」の理由を準備費用が発生する、人数制限がある等を添えると納得感が高まります。代理参加や譲渡の可否を記載することで、参加者の不満を和らげる効果もあります。コスト先払いの業種なら必須です。
例文3:段階的に返金額が変わるケース
期限内に返金を可能にする場合、イベント準備期間に合わせた柔軟な設定ができます。
例文としては「「お客さまのご都合によるキャンセルは、以下のキャンセル料を頂戴いたします。開催日の14日前まで:無料、開催日の13日前~8日前:参加費の20%、開催日の7日前~4日前:参加費の50%、開催日の3日前以降:参加費の100%」が適切です。
わかりやすく「何日前」だけでなく「何時間前」も併記することで、時間単位での判断がしやすくなります。顧客配慮型のイベントに向いています。
キャンセルポリシーを作成するときの注意点
法律・契約の観点を無視すると無効になる可能性があります。消費者契約法などに抵触するとトラブルにつながります。例を挙げると「いかなる場合も返金不可」としても法律で無効とされる場合があるので注意が必要です。契約書や利用規約は必ず専門家に確認してもらいましょう。
まとめ
キャンセルポリシーは損失防止、トラブル回避、信頼向上のために不可欠です。明確なルールを示すことで、顧客も安心して参加・予約できます。本記事で紹介した期限の設定、返金条件、例外対応、明記の場所、この4つのポイントを押さえるだけで、安心・安全なイベント運営が可能になります。ぜひこの記事を参考に、あなたのイベントに合ったキャンセルポリシーを作成してみてください。